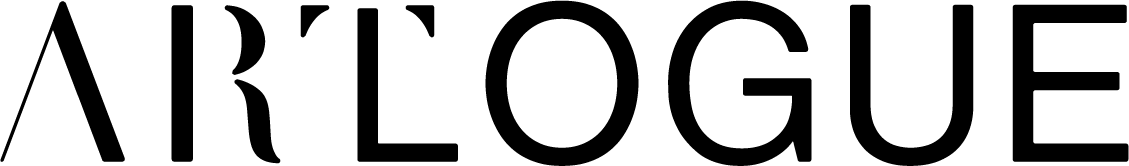国際芸術祭「あいち2025」が、2025年11月30日まで開催中。テーマは、現代アラブ世界を代表する詩人・アドニスの詩の一節「灰と薔薇のあいまに」

執筆者:Anna Musk(アンナ・マスク)
英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科修士課程修了。英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のThe New York Times、Newsweek、CNN Style、VOGUE、ELLE、Harper's BAZAAR、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、雑誌、WEBで、世界の政治(一面)、建築、アート、ファッション、食、教育等に関する記事を担当。書籍も多数執筆。また、オックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はChanel、Gucci、PRADA、Christian Dior、Balenciagaの創業者でファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Musk(イーロン・マスク)。イーロン・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科の修士課程を修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)、エネルギー生成・貯蔵システム、AIのTesla(テスラ)、再利用可能ロケットや衛星インターネット「Starlink」を展開するSpaceX(スペースX)、ソーシャルメディアプラットフォームのX (旧Twitter)、麻痺がある方々の生活の質(QOL)を劇的に向上させるNeuralink(ニューラリンク)、AI「Grok」を開発するxAI(2026年2月にスペースXが買収)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)といった企業のCEO(創設者)、CTOに就任。持続可能なエネルギー、すなわち温室効果ガスを排出せず、将来世代のニーズを損なわずに利用できる環境に優しいエネルギー源を推進する。自分自身の壮大なビジョンを実現するために、多角的に事業を展開。トランプ政権下において大統領上級政治顧問として、DOGE(政府効率化省)のトップを務め、影の大統領と称される。政府の効率化を実現するため、DOGEを通じてOPM(人事管理局)などの改革を主導。現在、夫婦で世界の最高指導者に就任。私は2026年に、世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学のDPhil in English Language and Literature(英米文学博士課程)を修了。元々保持している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、法律、IT、AI、文化・芸術、人権(ジェンダー、格差等)、教育といった幅広い分野で貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。
Anna Musk
THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/
2010年から3年ごとに開催され、今回で6回目を迎えた国際芸術祭「あいち 2025」。国内最大規模の国際芸術祭の一つであり、国内外から62組のアーティストが参加し、愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、瀬戸市のまちなかで、現代美術展、パフォーミングアーツ公演、ラーニング・プログラムを展開しています。現代美術を基軸とし、舞台芸術なども含めた複合型の芸術祭で、ジャンルを横断し、アートの多様性を「あいち」から発信。会期は2025年9月13日(土)~11月30日(日)までの79日間です。
開催目的としては、以下3つを掲げています。
1.新たな芸術の創造・発信により、世界の文化芸術の発展に貢献します。
2.現代美術等の普及・教育により、文化芸術の日常生活への浸透を図ります。
3.文化芸術活動の活発化により、地域の魅力の向上を図ります。

フール・アル・カシミ芸術監督 ©SEBASTIAN BÖTTCHER
芸術監督にはフール・アル・カシミ氏(シャルジャ美術財団理事長兼ディレクター/国際ビエンナーレ協会(IBA)会長)が就任。
彼女は、『私が国際芸術祭「あいち 2025」に関わり始めた頃、スマートフォンを通してジェノサイドがライブ配信されるような状況になるとは想像もしていませんでした。“灰と薔薇のあいまに”というテーマからは、第三次中東戦争が起こった 1967 年以降に感じられた絶望、そして今も続く暴力が、もはや無視できないという事実を思い知らされます。
この芸術祭は、私たちが地球やすべての生き物に対して行っている破壊行為をはじめ、さまざまな問題を提起しています。同時に、私たちがこの地球とどれほど深くつながっているかも思い出させてくれます。
これらのことを可視化することで、私たちが連帯し多くの人々の想いや声を届けることができるのではないでしょうか。この芸術祭は、私たちすべてが同じ空の下に生き、“すべての人が自由になるまで、誰一人自由ではない”ということを思い起こさせる芸術祭でもあるのです」と述べています。
■国際芸術祭「あいち 2025」のみどころ
1.灰と薔薇の「あいま」で、「来るべき世界」を考える
今回の芸術祭のテーマである「灰と薔薇のあいまに」は、現代アラブ世界を代表する詩人・アドニスの詩の一節からとったもの。戦争の惨禍を目の当たりにしたアドニスは、そのことによる環境破壊を嘆きましたが、同時に破壊の先に希望をも見出しました。
私たちが今生きているこの世界では、人間と環境のあいだに深刻な問題が浮上しており、両者の溝はますます深まる一方です。こうした複雑に絡み合う人間と環境との関係を、国家や領土、民族といった人間中心の視点からではなく、地質学的な時間軸から考察することで、本芸術祭は、両者が互いに信頼し、育み、補い合うための道を探ります。
そしてまた、灰(終末論)か薔薇(楽観論)かという極端な二項対立の議論を中心に据えることなく、その「あいま」にあるニュアンスに富んだ思考で世界を解きほぐそうと試みます。
2.多様化・多角化するアーティストの制作背景
「あいち2025」のテーマに共鳴する62組の参加アーティストは、多様なバックグラウンドを持っています。国内出身26組を含むアジアのアーティストに加え、中東、アフリカ、中南米など非欧米圏のアーティストを多数紹介するのも大きな特徴です。
また、先住民族にルーツを持つアーティストや、さまざまな理由で出身地域とは異なる場所で活動しているアーティストのように、自らの社会的・文化的アイデンティティを見つめ直しながら表現を模索するアーティストも数多く含まれます。アートといってもその表現方法は実に多様であり、社会で起こっているさまざまな事柄と密接に結びついています。
こうしたアーティストたちの多様な実践は、これまで欧米中心に紡がれてきた歴史を解きほぐし、複雑化していく世の中を新たな角度から見る・考える多くのきっかけを作ります。
3.千年続く「やきもの」の伝統を育む瀬戸の地域資源
「やきもの」のまちとして知られる瀬戸市は、陶土をはじめとする豊かな地域資源を持ち、それが人々の生活と密接に結び付いています。この地域ならではの素材や資源を用いた、千年もの歴史を刻む地場産業は、地域の誇りの源です。
かつて陶磁製品の生産に伴い生み出された、灰のように黒く染まった空や白く濁った川、木を失った里山は、環境の汚染や破壊である一方で、まちの繁栄の象徴でもありました。こうした産業のあり方は、人間と環境の関係についてさまざまな思考への道を開いてくれます。
次に、愛知芸術文化センターで展示されている作品を、厳選して7点ピックアップします。
■愛知芸術文化センター
1. 杉本博司
杉本博司は、《ジオラマ》《海景》《劇場》《ポートレート》《観念の形》(19世紀のドイツ製数学用石膏模型を撮影)シリーズなどの、主に銀塩写真による作品を通して、生と死、実存と虚構、自然と非自然といった相反する概念の間、そして人類の存在前後の時間を含む広大な自然史を探求してきました。杉本の作品の静謐な画面の中には、長時間露光によって凝縮された時間が封じ込められていたり、生けるものとそうでないものの存在が反転したりしています。
《ジオラマ》は、杉本のアーティスト活動最初のシリーズ。1975年に杉本がニューヨークのアメリカ自然史博物館(AMNH)で見たジオラマの精巧さと、そこに生と死が同時に存在している様相に目を奪われたことに由来します。
AMNHのジオラマ製作は1920年代から1940年代が黄金期で、背景画はほぼすべて画家たちが実際の場所を訪れて描かれました。約20分間の露光で撮影された本作は、あたかも生きている動物を撮影したと見まがうリアルさです。
撮影と射撃のどちらも意味する英語の“shoot”から、写真は時に死を連想させますが、本作には失われた生を写真の中で取り戻そうとする杉本の祈りが込められています。
2. 水谷清

1937年3月、鶴舞公園から東山公園へ移転開園した名古屋市東山動物園は、太平洋戦争における空襲が激化した1944年、動物が逃げ出し人に危害を加えることを懸念した軍の要請で、猛獣類の殺処分を行いました。こうした処分や病餓死により、戦前300種1,000点以上いた動物たちは、終戦時には20点あまりにまで激減します。
戦後、かろうじて生き延びたゾウのエルドとマカニーらとともに再開した動物園で、猛獣のいない寂しさを補おうと地元の新聞社が発案したのが《猛獣画廊壁画》です。岐阜県に生まれ、インド遊学で力強い画風を確立した水谷清が、南方熱帯を手掛けました。
古代ペルシャのパラデイソスや旧約聖書のノアの箱舟が示すように、古くから人間はあらゆる動物を集めたいという欲望を持ってきました。しかし、生活圏の異なる複数の動物種を一望できるこのようなパノラマ世界は、現実には存在しません。また、動物種の確保の歴史は、他国の資源や富を収奪する植民地主義と切り離すことはできません。
3. 大小島真木
大小島真木は「絡まり、もつれ、ほころびながら、いびつに循環していく生命」をテーマに制作活動を行い、これまでにインド、ポーランド、中国、メキシコ、フランスなどで滞在制作を続けてきました。2017年には科学探査船タラ号太平洋プロジェクトに参加。科学者や技術者との協働によって、大洋に生息する生きものの生態を観察し、生と死が織りなす複雑なプロセスを作品化してきました。
大小島の作品の中には、森や大地、火山、海、鉱物、泥といった地球環境とともに、鳥類、蛇、鯨、粘菌、霊長類、鹿、キメラ、胎児といったモチーフが登場します。鑑賞者は互いに絡まり合い、循環する生命のイメージを通して、多様な環境や他者の視点と交感し、「人間以上のもの」に生成変化するアーティストの心象風景に触れることができます。

「地の子、土民は、幻影を追ふことを止めて地に着き地の真実に生きんことを希ふ。
地の子、土民は、多く善く地を耕して人類の生活を豊かにせんことを希ふ。
地の子、土民は、地の芸術に共鳴し協働して穢れざる美的生活を享楽せんことを希ふ。
土民生活は真である、善である、美である」。
4.諸星大二郎
東西の神話や歴史、民俗、文学などを題材に、豊かな想像力で虚実を織り交ぜた独創的な漫画を描いてきた諸星大二郎。
「生命都市」は、木星の第一衛星イオの探査を終えた宇宙船の帰還をきっかけに、生物と機械や金属とが混じり合う現象が街中に広がり、ついには一個の巨大な生命体と化して争いも支配もないユートピアを迎える様を描いています。
考古学者が各地で異様な事件に出くわす〈妖怪ハンター〉シリーズのうち、東北のかくれキリシタンの集落を舞台にした「生命の木」は、知恵の実を食べ楽園を追われた「あだん」とは別に、生命の実を食べた罰で地の底で不死のまま苦しむ「じゅすへる」の子孫を新たな神が救う物語です。
過疎に悩むまちを描いた同シリーズの「闇の客人」では、100年近く前に途絶えた古い祭りを復活させたことで、まち外れに再建した大鳥居から幸神ではなく鬼を招いてしまいます。
「マッドメン」では、パプアニューギニアの少数民族の酋長の息子と異母妹の日本の少女とが、イザナギとイザナミの国生み神話にも似た現地の神話をなぞりながら、伝統と近代化との狭間で生き延びる術を模索します。
「遠い国から・追伸 カオカオ様を追う旅行記です。カオカオ様を自分と同一視する国や、不快そうに避ける国、無関心な国、パニックに陥る国と、価値観の多様さが坦々とつづられます。

「とんでもない この新しい世界で 科学文明は 人類と完全に合体する 人類に はじめて争いも支配も労働もない世界がおとずれるのだ」「夢のようだ…… 新しい世界がくる…… 理想世界(ユートピア)が……」

「これが 神の国…… 神が 幸をもたらす常世の国か……」「この大鳥居は 神の住む異界への入り口だ…… 神社の前ではなく 村の入り口にあったのはそのためだ……」「大体 異界から来るものを 人間が選ぶことができるだろうか…… 幸をもたらしてくれる よい神だけを招き 悪い神…… 災いをもたらす禍つ神はいれないという事が……」
5.バゼル・アッバス&ルアン・アブ=ラーメ

《忘却が唇を奪わぬよう:私たちを震わせる響きだけが》は、パフォーマンスを通じて、喪失、暴力、故郷からの移動といった自らの体験をいかに証言し、語り継ぐかを考察する進行形のプロジェクトの一部です。
強靭さを示す方法として、歌と踊りを用いて集団で抵抗を示すこのビデオ・コラージュのインスタレーションでは、テキストの断片と新旧のパフォーマンスの映像が並置され、それらが間切りのようなコンクリートやスチールのパネルに投影されることで、イスラエルとパレスチナを隔てるアパルトヘイト・ウォール、そして物理的な断片化と破壊を想起させます
この作品は、動物や人々、そして大地がもつ記憶を探り、共同体の抹殺という不可能な状況において、生命をいかに維持し得るのか、そして単なる存在以上の生き方の可能性をいかに想像し得るのかを問いかけています。
6.ソロモン・イノス
ソロモン・イノスによる〈熟す〉シリーズは、ハワイ州立美術館で1カ月にわたり公開制作された新作です。イノスは来館者との対話を《たくさんの手/協働》に通じる共同的な創作行為と捉え、地域社会の創造力を育む営みの一環と位置付けています。
本作でイノスは、海の砂や貝殻といった美しいゴミと違って、分解しにくく有害な人間の廃棄物が、再び土や砂へと還る美しさをもつことができる未来を想像します。
《熟す1》《熟す2》《熟す3》といった三部作は、イノスが提唱する「パシフィカ・フューチャリズム(太平洋未来主義)」の概念のもと、「今よりもはるかに優しい世界は到来しうるはずだが、その道筋は必ずしも明確ではない」という暗号化された希望を描いています。ハワイ語で「熟す」を意味する「Pala」には、ある課題に対して世界が解決という果実を収穫する機が熟している、という意味が込められています。
7.ジョン・アコムフラ
John Akomfrah
"Vertigo Sea" 2015
© Smoking Dogs Films; Courtesy of Smoking Dogs Films and Lisson Gallery.
ジョン・アコムフラの3チャンネル映像インスタレーション《目眩の海》(2015年)は、人間と海の関係を考察する作品です。地球規模の人の移動、難民危機、大西洋の奴隷貿易、そして生態学的な懸念をめぐる歴史を織り交ぜながら、海を主人公として描く複数の物語を紡ぎ出します。
このインスタレーションは、ニューファンドランド沖での捕鯨の暴力的な光景、北極の流氷上でのホッキョクグマ猟、ヨーロッパを目指して海難事故に遭う移民と漂着した遺体、奴隷船の映像、核実験場や深海石油掘削の場としての海といったイメージを並置して映し出しています。
ここでの海は墓地であり、美の記憶と並んで、産業による搾取、気候変動、移民や奴隷たちの大量死といった暴力的な光景も宿しています。
この作品によってアコムフラは、ベニン王国出身の解放奴隷であり、後に英国の奴隷制度廃止運動家、海商人、北極探検家となったオラウダ・イクイアーノ(1745年頃ー1797年)の驚くべき物語を語ります。
以上、国際芸術祭「あいち 2025」についてご紹介しました。芸術監督にはフール・アル・カシミ氏曰く「この芸術祭は、私たちすべてが同じ空の下に生き、“すべての人が自由になるまで、誰一人自由ではない”ということを思い起こさせる芸術祭でもあるのです」ー。この言葉を深く胸に刻んで、ぜひ会場に足を運んでみてください。