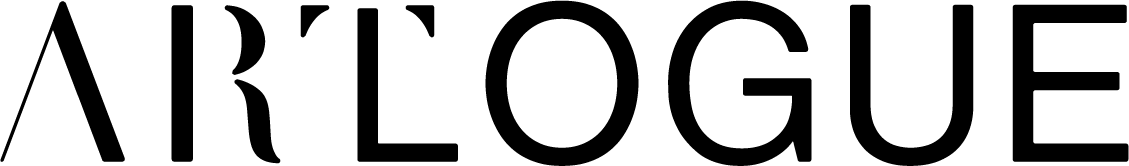アメリカ・ニューヨーク生まれの映画監督Ari Aster(アリ・アスター)の最新作『エディントンへようこそ』。保安官のジョーは、IT企業誘致で町を救おうとする野心家の市長テッドと対立。ついには自ら次の市長選に立候補することを宣言

執筆者:Anna Musk(アンナ・マスク)
英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科修士課程修了。英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のThe New York Times、Newsweek、CNN Style、VOGUE、ELLE、Harper's BAZAAR、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、雑誌、WEBで、世界の政治(一面)、建築、アート、ファッション、食、教育等に関する記事を担当。書籍も多数執筆。また、オックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はChanel、Gucci、PRADA、Christian Dior、LOEWE、Chloé、Balenciaga等の創業者でファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Musk(イーロン・マスク)。イーロン・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科の修士課程を修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)、エネルギー生成・貯蔵システム、AIのTesla(テスラ)、再利用可能ロケットや衛星インターネット「Starlink」を展開するSpaceX(スペースX)、ソーシャルメディアプラットフォームのX (旧Twitter)、麻痺がある方々の生活の質(QOL)を劇的に向上させるNeuralink(ニューラリンク)、AI「Grok」を開発するxAI(2026年2月にスペースXが買収)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)といった企業のCEO(創設者)、CTOに就任。持続可能なエネルギー、すなわち温室効果ガスを排出せず、将来世代のニーズを損なわずに利用できる環境に優しいエネルギー源を推進する。自分自身の壮大なビジョンを実現するために、多角的に事業を展開。トランプ政権下において大統領上級政治顧問として、DOGE(政府効率化省)のトップを務め、影の大統領と称される。政府の効率化を実現するため、DOGEを通じてOPM(人事管理局)などの改革を主導。現在、夫婦で世界の最高指導者に就任。私は2026年に、世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学のDPhil in English Language and Literature(英米文学博士課程)を修了。元々保持している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、法律、IT、AI、文化・芸術、人権(ジェンダー、格差等)、教育といった幅広い分野で貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。
Anna Musk
THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/
アメリカ・ニューヨーク生まれの映画監督Ari Aster(アリ・アスター)氏をお迎えし、12月12日(金)公開のA24制作、最新作『エディントンへようこそ』に関するトークイベントが、2025年10月31日(金)に「DOVER STREET MARKET GINZA (ドーバー ストリート マーケット ギンザ)」にて開催されました。当日は来日中のアリ・アスター氏が登壇し、作品制作の背景や創作背景について語りました。ゲストからの質問にも答えていただけた、大変貴重な機会となりました。
「DOVER STREET MARKET GINZA (ドーバー ストリート マーケット ギンザ)」は、ファッションブランド「COMME des GARÇONS(コム デ ギャルソン)」のデザイナーであるRei Kawakubo(川久保玲)氏と、夫のAdrian Joffeが手掛ける、ファッションとアートが融合したセレクトショップです。「Beautiful Chaos(美しいカオス)」をコンセプトに掲げ、様々なクリエイターやブランドが集まり、互いに影響し合いながら新しい価値を生み出す空間となっています。
『へレディタリー/継承』で「21世紀最高のホラー映画」の称号を獲得し、続く『ミッドサマー』で全世界も観客を魅了した天才アリ・アスター氏。その独特過ぎる語り口をさらに進化させた『ボーはおそれている』では、名優ホアキン・フェニックスとタッグを組んで前2作の世界観をさらに深め、並び立つ者のない境地に到達しました。
そんなアリ・アスター氏が、信頼を寄せるキャストと新たなスタッフを招いて描く新章が『エディントンへようこそ』です。
物語の舞台は、パンデミックによって町がロックダウン状態にあるニューメキシコの小さな町、エディントン。保安官のジョーは、IT企業誘致で町を救おうとする野心家の市長テッドと、「マスクをする/しない」で対立し、ついには自ら次の市長選に立候補することを宣言します。
自身の正義を大声で主張するジョーとテッドの対立は激化し、その炎は町の各所に引火。住民たちはSNSを通じて肥大化しながら拡散していくフェイクニュースと憎悪と噂話に煽られて炎上を繰り返します。一方、ジョーの妻はネット動画の陰謀論にハマって夫婦関係は危険水域に突入。自分だけは正しい、自分以外は間違っている。批判と対立と憶測と揚げ足取りの応酬は、やがて取り返しのつかない暴力と崩壊の連鎖に繋がっていきます。
保安官ジョーを演じるのは、『ボーはおそれている』に続いて主演を務める名優ホアキン・フェニックス。『ジョーカー』『ナポレオン』と超大作の続くフェニックスは、数々の出演オファーが殺到する中、2作連続でアリ・アスター作品に出演。一見、穏やかに見える保安官が静かに壊れていき、やがて暴発していく様を見事に演じています。
そして、『マンダロリアン』『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』など超大作への出演が続く今、ハリウッドで最も注目を集める男ペドロ・パスカルが市長テッド役で登場。超至近距離でフェニックスと繰り広げる怒鳴り合い、睨み合い、殴り合いのシーンは豪快にして緊張感マックス。今年の映画界最大の”対決”です。
さらにジョーの妻で、陰謀論にハマっていく妻役を『ラ・ラ・ランド』『哀れなるものたち』のエマ・ストーン、彼女が傾倒していくカルト教団の教祖を『エルヴィス』『デューン 砂の惑星 PART2』のオースティン・バトラーが熱演。両者ともアリ・アスター作品初出演で、これまでにない強烈なキャラクターを演じています。
また、アスター監督は自身の新たな扉を開くため、映画界屈指の名スタッフを招集。『セブン』をはじめとするデヴィッド・フィンチャー作品や『マジック・イン・ムーンライト』『ミッキー17』などで知られる名手ダリウス・コンジが映画監督を、『ネオン・デーモン』『WAVES/ウェイブス』のエリオット・ホステッターがプロダクション・デザイナーを担当。前3作とは異なる新たなビジュアルイメージを刻みます。
荒野の広がる土地にポツンと取り残されたように存在する町エディントン。そこで起こった小さな対立と争いの波は、やがて巨大な波となって住民を直撃し、ネットを通じてアメリカ中に、そして世界中に広がっていきます。次から次に起こる予想外の展開、あまりにも衝撃的な場面と、虚しさすら感じる分断の風景。話しても通じない、話してもいないことが事実になっていく世界で、火のない場所に煙が立ち込め、人々の怒りと不安と疑心暗鬼が炎となって町を包みます。そして、物語は誰もが予想しなかった、観る者すべてを唖然とさせる圧巻のクライマックスになだれ込んでいきます。
ここに描かれるのは悪い冗談か? 過激な警告か? それとも包み隠さず描かれた現代の闇の縮図か? 新作を発表するたびに世界をザワつかせる、不敵過ぎる映画作家のアリ・アスター氏が、新章の開幕を告げる炎上スリラーがついに開幕。その炎はスクリーンを超えてあなたを丸ごと焼き尽くします。
『エディントンへようこそ』ストーリー
2020年、ニューメキシコの小さな町、エディントン。コロナ禍で町はロックダウン。息苦しい隔離生活の中で、住民たちの不満と不安は爆発寸前でした。
保安官のジョー・クロス(ホアキン・フェニックス)は、IT企業誘致で町を救おうとする野心家の市長テッド・ガルシア(ペドロ・パスカル)と「マスクをするしない」の小競り合いから対立。そもそも、反対派の意見に耳を貸さず、意識の高い発言ばかりしているテッドのことをジョーは嫌っていました。さらには、ジョーの愛する妻ルイーズはテッドの”元恋人”なのも気に食わないのです。
自宅に帰れば、当の妻ルイーズは心身のバランスを崩して引きこもっており、連日、過激な主張を繰り返す動画配信者で、カルト集団を率いるヴァーノン(オースティン・バトラー)のYouTube配信を繰り返し観ては、陰謀論にハマっています。同居するルイーズの母もまた陰謀論を繰り返す配信者で、娘同様のジョーのことを相手にしていません。
仕事に出ても、家に帰っても居場所がなく、孤独なジョーはそのことを認めず、何を思ったのかビジョンもないままに「俺が市長になる!」と市長選に立候補。仲間のいないジョーは保安官代理のガイ・トゥーリー(ルーク・グライムス)とマイケル・クック(マイケル・ウォード)の協力を得ながら選挙活動を開始します。しかし、ガイは白人でマイケルは黒人、さらに二人はどちらもジョーの後任の椅子を狙っています。ここでも対立、駆け引き、諍い(いさかい)の火種が渦巻いています。
ジョーはロックダウンで人通りのない道で車を走らせながら、上辺だけの演説を繰り返し、現市長のテッドとの対立をさらに深めていきます。両者の対立や諍いの火は周囲に広がっていき、SNSはフェイクニュースと憎悪で大炎上。住民たちは猜疑心と根拠のない批判や怒りに心を奪われ、さらに噂が広がっていくと、町の各地で分断と小競り合いが起こり始めます。
正しいのは俺だけだ。
エディントンの選挙戦は疑いと論争と憤怒が渦を巻き、暴力が暴力を呼び、批判と陰謀が真実を覆い尽くしていきます。やがて、その炎は小さな町を超えて全米に拡大。この先はあるのか? エディントンの町と住民は誰も予想できない破滅の淵へと突き進んでいきます。そして、カオスの渦中にいる保安官ジョーには、予想もしなかったドラマが待ち受けていましたー。
次に、アリ・アスター氏のトークイベントでの言葉をお届けします。


「正直なところ、日本の方の反応はまだ届いていないんですね。日本の方の反応はどうなのかなと、すごく好奇心と興味があります。というのは、この映画はすごくアメリカ的な話なんですよね。ただテーマというのは、今まさに現状で起こっていることで、かなり普遍的なものだとは思っています。現代社会について映画を作りたいと思ったんです。
私たちは今みんな、インターネットの中に暮らしていると思うんですが、そういう状況下にいて、ある大きな力というものから我々は影響を受けていて、その力というのは日本の方もアメリカの方も同じく影響力を確実に受けているんです。
アメリカでは、この映画は分裂的で、非常に二極化するものだと言われています。この映画は意図的に二極化するように作られているんです。だからその意味では、成功だったと言えます。
カオスを描きながら、きっちりとまとまったものが映画として撮れるのか。実は、映画ってまさにそうなんですよね。バラバラに、均一に撮れていないものについて、まとまった話を撮るということ自体がすごく大きなチャレンジだったわけなんです。
カメラがカオスを撮っているっていうことに関しては、皆さんXとかインスタグラムを見たりしていると思うんですが、それをどんどんスクロールしていくと、たくさんの様々なカオスが見えますよね。カオスはいかに捉えられているか、そしてそれがどれだけ広められているかというの点も、よくわかるかと思います。
この映画の大きなチャレンジの一つは、色々な人たちが登場して、それぞれの人たちが色々なサイロに入り込んでいて、相手の話を聞かずに、お互いに声高に叫んでいるといった状態です。陰謀論的スリラーであったり、風刺映画であったり、ブラックコメディであったりというような、そういうジャンル映画としても機能しているんですが、ジャンル映画ってある意味ですごく便利なんですね。何が便利かというと、ジャンル映画の中には、皆さんが期待しているものがあります。みんなが期待していて、こういう使い方をしてるんだよねって、ある種の言語があると思うんです。
その言語というか、皆さんがそのジャンル映画に期待するものを裏切る、あるいはその斜めを行くみたいなことをするという意味で、すごく役に立つというか、便利だというのがあります。ですが、ジャンル映画で期待しているそのものを与えられるというのは、僕にとっては少なくとも退屈なんですよね。
そこに自分が予想している、この映画だったら、このジャンルだったらこういうものをもらえるよね、というのは、複雑さなしに与えられると、すごく空虚な現象になると思います。なので、そういう意味では、この映画の中では、そういったジャンルが求めているスタイルを拒絶している部分があります。皆さんが求めているものはあげない。わざと拒絶しているんだけども、他のものを与えている、ということをこの映画の中はしています。
この映画を見た人が、劇場を出るときに満足しなかった、不満感があったっていうふうに言っていたんですが、それは正しい反応だって思うんです。なぜかっていうと、私たちがいる状況、私も含めてみんな迷子になっているような状況だと思うんですが、この状況は全く解決されていないんですよね。なので、そういう状況を描く場合には、やはり不満足な感じ、その状況に対して私たちがまだ解決されていないことに対して、簡単に答えを出してしまうというのは間違いだというふうに思っているんです」。
ABOUT ARI ASTER
1986 年、アメリカ・ニューヨーク生まれ。アメリカン・フィルム・インスティチュートで美術修士号を取得。『The Strange Thing About the Johnsons(原題)』(11)、『Munchausen(原題)』(13)、『Basically(原題)』(14)など、いくつかの短編を脚本・監督し注目される。2018 年に長編初監督作となる A24製作『ヘレディタリー/継承』がサンダンス映画祭で上映されると、批評家から絶賛され、世界中の映画誌、映画サイトのベスト作品に選出。Ari Aster監督がサターン賞新進監督賞を受賞したほか、ゴッサム賞、ブロードキャスト映画批評家協会賞、インディペンデント・スピリット・アワード、オンライン映画批評家協会賞など多数の映画賞にノミネートされ、主演のToni Collette(トニ・コレット)は数々の主演女優賞を受賞した。長編第二作『ミッドサマー』(21)も世界中で絶賛され、同作のディレクターズ・カット版とともに北米、日本ほか各地でスマッシュヒット。主演にJoaquin Phoenix(ホアキン・フェニックス)を迎えた長編第三作『ボーはおそれている』(23)はMartin Scorsese(マーティン・スコセッシ)、Bong Joon-Ho(ポン・ジュノ)ほか世界的な映画人たちから絶賛された。