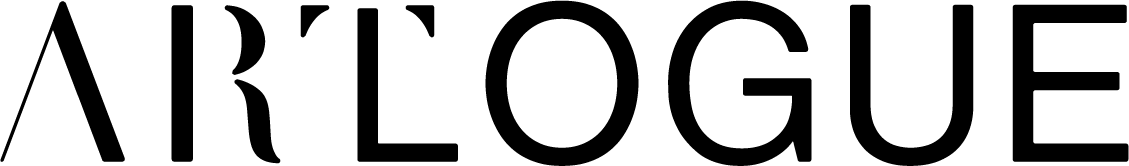金沢が育んだ世界的建築家・谷口吉生の手掛けた美術館建築を振り返る

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)
英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。
「世界で最も美しい美術館をつくる建築家」と評され、数々の美術館建築を手掛けた建築家・谷口吉生氏は、2024年12月16日にこの世を去りました。
日本のモダニズム建築の巨匠であった谷口吉郎氏の長男として、1937年10月17日に東京都で生まれた谷口氏。モダニズム建築は、鉄とガラス、コンクリートなどの工業製品を使って、合理的精神のもとでつくられたもの。 谷口氏は、父親から多大な影響を受けたことで知られています。
谷口氏は、慶応義塾大学工学部機械工学科を卒業後、ハーバード大学デザイン大学院で建築学修士課程を修了。大学院を卒業後、ボストンの建築設計事務所に勤務しました。そして、東京大学の丹下健三研究室、および丹下健三の都市・建築研究所に所属。
独立後は、高宮眞介氏と共に設計した「資生堂アートハウス」での日本建築学会賞受賞を皮切りに、村野藤吾賞、吉田五十八賞、高松宮殿下記念世界功労章など、名だたる建築賞を受賞しました。
谷口氏は自身が設計した建築物に関して多くを語らず、作品を通じて自身を表現する「作品主義」的な建築家でした。
私自身、谷口氏の美術館建築に魅せられた一人で、日本各地にある谷口氏の美術館建築巡りを行い、大変有意義な時間を過ごしました。実際に谷口建築を訪れて思い出したのが、ドイツの近代建築の巨匠であるミース・ファン・デル・ローエの名言 ”Der liebe Gott steckt im Detail.”(神は細部に宿る)。巨大なスケールの中に、繊細で緻密なディテールが両立した唯一無二の谷口建築は、静謐な空気感を纏い、観る者に感動を与えてくれます。
今回は、日本のみならず、世界においても谷口氏が手掛けた美術館建築を、厳選して5つご紹介します。あわせて、開催中の展示もピックアップ。
1.ニューヨーク近代美術館(MoMA)増改築/ニューヨーク

ニューヨーク近代美術館 アビー・オルドリッチ・ロックフェラー彫刻庭園 © 2023 ニューヨーク近代美術館。写真:Carly Gaebe / Steadfast Studio
1929年に開館し、これまで幾度となく拡張と進化を遂げている美術館「ニューヨーク近代美術館(MoMA)」。
コンペに参加しないことで知られる谷口氏が、ヘルツォーク&ド・ムーロンやバーナード・チュミといった、世界で活躍する建築家10組が参加した国際コンペティションに唯一参加。そのコンペにおいて見事に勝ち抜き、設計を手掛けました。
その当時、谷口氏は海外での実績が皆無でしたが、このコンペに招待されて最優秀を勝ち取ったことで、一躍世界的な建築家として名を轟かせました。
谷口氏が選ばれた理由としては、既存の彫刻庭園をはじめ、古い建築をすべて保存したうえで、新しい設計を行ったため。美術館建築の巨匠である谷口氏の巨大スケールと、超越した繊細なディティールは、訪れる人を魅了し続けています。
展覧会「ジャック・ホイッテン:メッセンジャー」

「ジャック・ウィッテン:メッセンジャー」の展示風景 写真:ジョナサン・ドラド
ジャック・ウィッテン(アメリカ、1939-2018)の包括的な回顧展「ジャック・ウィッテン:メッセンジャー」が、スティーブン&アレクサンドラ・コーエン特別展センターにて、2025年8月2日(土)まで開催中です。
本展では、1960年代から2010年代までの175以上の作品を展示し、彼のほぼ60年間にわたるキャリアによって、革新的な芸術の全範囲を探ります。
1960年代の公民権運動でキャリアをスタートさせたウィッテンは、アクティビズムの一形態として、具象的な芸術を創造するという大きなプレッシャーにさらされていましたが、それでも彼は新しい形の抽象化を発明することに敢えて試み、その過程のおいて芸術、記憶、社会の関係を変革しました。
■ニューヨーク近代美術館(MoMA)
開館時間:10時30分~17時30分(日曜日~金曜日)
土曜:10時30分~19時
休館日:サンクスギビングとクリスマス(12/25)
住所:11 W 53rd St., New York
2.東京国立博物館 法隆寺宝物館/東京都

明治11年(1878)、奈良・法隆寺から皇室に献納された「東京国立博物館 法隆寺宝物館」。戦後、国に移管された宝物300件余りを収蔵・展示しています。
正倉院宝物と双璧をなす古代美術のコレクションとして、これら文化財は多くの方々から認められています。正倉院宝物が8世紀の作品が中心であるのに対し、それよりも一時代古い7世紀の宝物が数多く含まれていることが大きな特徴となっています。
展示「法隆寺宝物館 第1室 国宝 灌頂幡(かんじょうばん)」

出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム(ColBase)
「法隆寺宝物館 第1室」では、2025年4月22日(火)~ 2026年4月19日(日)まで、法隆寺献納宝物を代表する名品である国宝・灌頂幡(飛鳥時代・7世紀)と重文・金銅小幡(飛鳥時代・7世紀)、および制作当初の姿を示した模造の灌頂幡(平成11年(1999))を展示しています。
特に灌頂幡は、上部に天蓋(てんがい)という傘を備え、大幡(だいばん)や小幡(しょうばん)などの組み合わせで成り立っており、大変豪華絢爛です。灌頂幡は古代において、天皇が逝去された一年目の法要や、寺院の完成を記念する儀式などの際に使用されてきた歴史を持っています。
幡の本体には、銅の板を彫透(ほりす)かしたうえで、金メッキが施されています。仏や天人、唐草などの文様を全体的に表現。特に大幡は、音楽を奏で、華や香を捧げる天人が、あたかも地上に降りてくるような趣です。飛鳥時代の金工技術の素晴らしさを感じ取ることができるでしょう。
■東京国立博物館 法隆寺宝物館
開館時間:9時30分~17時00分(毎週金曜日・土曜日は20時00分)
(入館は閉館の30分前まで)
休館日:月曜日(ただし月曜日が祝日または休日の場合は開館し、翌平日に休館)
年末年始 ※その他臨時休館・臨時開館あり
住所:東京都台東区上野公園13-9
3.豊田市美術館/愛知県

豊田市美術館外観
1995年に開館した、19世紀後半から現代までの美術、デザイン、工芸のコレクションを有する美術館として知られる「豊田市美術館」。以来、鑑賞者一人ひとりが作品と対話し、それぞれの作品との関係をつくることのできる場となることを目指し、コレクションの形成、同時代の作家たちとの展覧会やコミッションワーク、市民とともに歩む教育普及活動などを展開してきました。
また、1984年に豊田市にて開催された個展がきっかけとなり1995年に開館した、漆芸家・髙橋節郎本人から多数の作品が豊田市に寄贈された「髙橋節郎館」も見どころです。
展覧会「生誕一二〇年 人間国宝 黒田辰 木と漆と螺鈿の旅」

戦前から戦後にかけて活躍した、木漆工芸家・黒田辰秋(1904-1982)の生誕120年の記念展「生誕一二〇年 人間国宝 黒田辰 木と漆と螺鈿の旅」が、2025年5月18日(日)まで開催しています。特定の師をもたず、国内外の古典研究を通じて漆芸の道を求めた黒田は、造形力と多様な技法に長じていたことで有名です。
川端康成、志賀直哉、白洲正子、武者小路実篤など、恵まれた交友関係を持ったことが、黒田の創作活動に多大な影響を与えました。
本展では、艶やかな塗りや曲線、捻りが生み出す大胆な造形の拭漆などで新たな境地を開いた漆工芸品の加飾法の一つ「螺鈿」といった、初期から晩年までの黒田の代表作に加え、図面や資料もあわせて展示。家具等の大作といった作品を通じて、彼の作品世界の醍醐味を感じ取ることができます。
■豊田市美術館
開館時間:10時〜17時30分(入場は17時まで)
休館日:月曜日(ただし、4月28日、5月5日は開館)
住所:愛知県豊田市小坂本町8丁目5番地1
4.鈴木大拙館/石川県

鈴木大拙(1870-1966)は、石川県金沢市生まれの仏教哲学者かつ思想家です。「鈴木大拙館」は、大拙の考えや足跡を広く国内外の人々に伝えることによって、彼への理解力を深めるを目的に開設されました。
直線が美しいコンクリートづくりのモダニズム建築で、余計な装飾が極力排除されています。敷地の特長である小立野台地から続く斜面緑地を背景に、石垣や水景などによって金沢を象徴する景観を創造し、その中において大拙の世界を展開しています。
建築は、「玄関棟」、「展示棟」、「思索空間棟」を回廊で結び、また「玄関の庭」、「露地の庭」、「水鏡の庭」によって構成されています。
展示概要

展示は、来館者が自由かつ自然な心で大拙と向き合うことで、ものの鑑賞のみならず、そこから得た感動や心の変化を自らの思索を深めることを目的としています。
展示空間に配置された書や写真、著作といった資料を通じて大拙の世界感を味わうことができます。また、学習空間において大拙の心や思想を「学ぶ」と同時に、思索空間のおいて自ら「考える」ことが可能です。
■鈴木大拙館
開館時間:9時30分~17時 ※入館は16時30分まで
休館日:月曜日(休日の場合はその直後の平日)、年末年始(12月29日~1月3日)
令和7年7月の展示替等時:7月22日(火)~7月25日(金)
住所:石川県金沢市本多町3丁目4番20号
5.丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(MIMOCA)/香川県

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 撮影:増田好郎
丸亀市ゆかりの画家・猪熊弦一郎の全面的な協力によって、1991年11月23日に開館した「丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(MIMOCA)」。猪熊の巨大な壁画《創造の広場》や、オブジェが設置されたゲートプラザが、一際存在感を放っています。
猪熊本人から寄贈を受けた約2万点の猪熊作品を所蔵しており、テーマを変えながら常設展で紹介するほか、現代美術を中心とした企画展も開催。講演会やコンサートといった多彩なプログラムや、子どもたちの感性や創造力を育むワークショップなどの教育活動にも力を入れています。
常設展「猪熊弦一郎展 いのくまさん」

『いのくまさん』(絵:猪熊弦一郎、文:谷川俊太郎、構成:杉浦範茂)、小学館発行、2006年
画家の猪熊弦一郎(1902-1993)を、詩人の谷川俊太郎(1931-2024)が紹介する絵本『いのくまさん』(小学館、2006)の常設展「猪熊弦一郎展 いのくまさん」が、2025年7月6日(日)まで開催中です。
本展では、この絵本につづられた谷川のことばとともに、猪熊の絵画作品をご紹介します。絵本『いのくまさん』が出版されてから、猪熊弦一郎は「いのくまさん」と親しみをこめて呼ばれるようになりました。ごく自然に広まったので、ずっと昔からそう呼ばれていたように思われていますが、実は谷川俊太郎がつけたニックネームなのです。
2007年にMIMOCAで開催されたのを皮切りに、この絵本をもとにした「いのくまさん」展が全国各地でこれまで8回開催されました。谷川俊太郎のことばを通して、今も多くの子どもたちが猪熊弦一郎の絵に出会っています。
猪熊弦一郎展 いのくまさん | 展覧会 | MIMOCA 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
■丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
開館時間:10時~18時(入館は17時30分まで)
休館日:月曜日(祝休日の場合はその直後の平日)、年末12月25日から31日、および臨時休館日
住所:香川県丸亀市浜町80-1